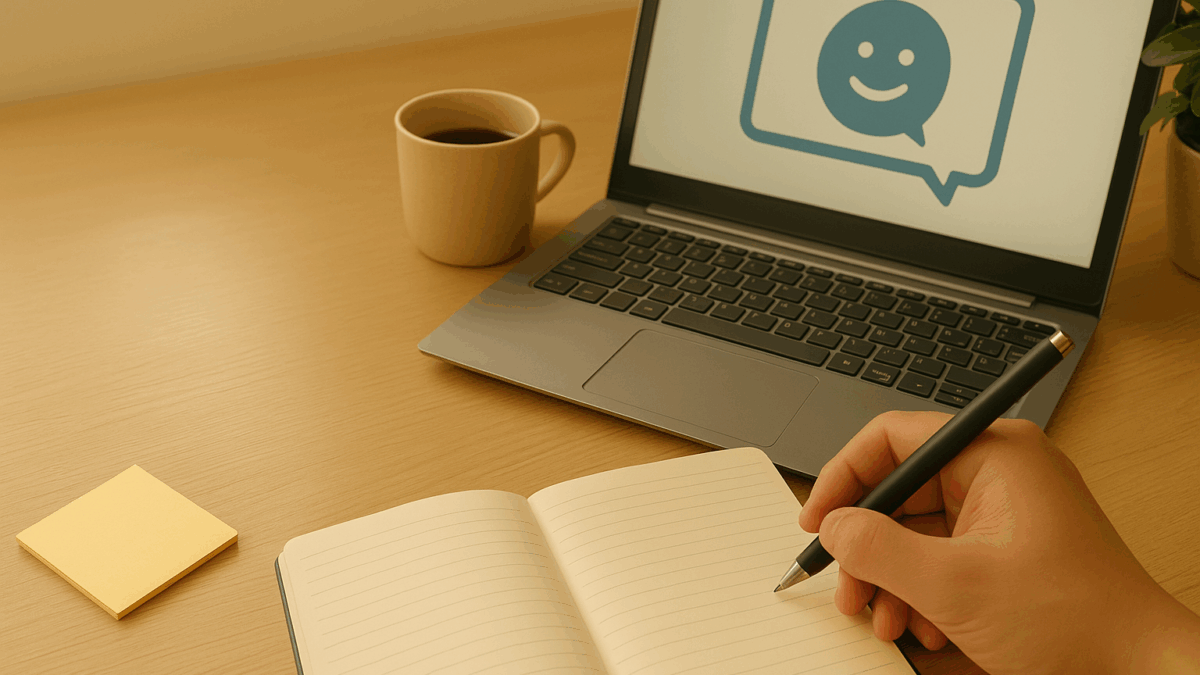AIが登場してから、私たちは一人でも大量のアイデアを出せる時代になりました。
プロンプトを入力するだけで、驚くほど多様な発想を提案してくれる。
これまではチームで何時間もかけていたブレインストーミングが、たった数分で一人でもできるようになったのです。
でも、ここで少し立ち止まって考えたくなりました。
AIから出てきたアイデアをそのまま採用しているだけで、本当に「自分のアイデア」と呼べるのでしょうか?
たしかに、良いプロンプトを作る力も重要です。
しかし、アイデアは「出す」だけでなく、「ふくらませていく」ことでもっと面白くなるのではないか…?
今回は、そんな視点から、
「AIが出してくれたアイデアに、自分の手でふくらませていく方法」についてご提案します。
そして、その手助けになるツールとして、アイデアプラント製品の活用例もご紹介していきます。
AIアイデアの「鵜呑み」がつまらない理由
AIが出してくれるアイデアは、とても便利です。
たくさんの選択肢を短時間で提示してくれるのだから、ついそのまま採用したくなってしまいます。
でも、出てきたものをそのまま受け入れているだけでは、
「自分で考えた」という実感が持てなくなってしまうのではないか――そんな危うさも感じます。
実際、私自身も、他の人からAIを使って生成したアイデア群を渡されたことが何度もあります。
そのとき、言葉にしづらい違和感を覚えました。
「これは……?」という戸惑いだけが先に立ち、
行間を必死に読まなければならないようなストレスのようなものを感じたのです。
そもそも、「これを私に伝える意図は何なのだろう?」という、少しもやっとした気持ちも残りました。
みなさんも、そんなふうに感じたことはないでしょうか?
アイデアは、単に出されたというだけでは、
その背景や意図を共有できなければ、相手にとって意味のあるものにはなりにくい。
だからこそ、AIからもらったアイデアに、自分なりの考えや視点を加えることが大切なのだと思います。
どんなに魅力的なアイデアに見えても、
「これ、本当に自分が選びたいものなのか?」
「どんな視点でこのアイデアを面白いと感じたのか?」
そんな問いかけを挟まないまま進んでしまうと、
単に「AIが出してくれたアイデアを拾っただけ」で終わってしまうかもしれません。
AIはきっかけをくれる存在です。
でも、そこに自分なりの意味づけやアレンジを加えていくことで、初めて「自分のアイデア」になっていくのだと思います。
アイデアに“自分の手”を加えることの意味
AIが出してくれるアイデアは、きっかけとしては素晴らしいものです。
でも、そのまま受け取るだけでは、自分の中で「なぜこれがいいと思うのか」「どう活かせるのか」という視点が育ちません。
アイデアは、もらった瞬間に完成するものではない。
そこから、自分なりに問い直し、広げたり、ふくらませたりしながら、ようやく自分のものになっていくのだと思います。
たとえば、こんな問いかけをしてみてもいいかもしれません。
• 「このアイデアに、自分が共感できるポイントはどこだろう?」
• 「これを実現するとしたら、どんな工夫が必要だろう?」
• 「もしこれを組み合わせたら、もっと面白くなるか?」
そんなふうに、自分の思考を重ねていくプロセスこそが、
アイデアに命を吹き込む作業なのだと思います。
AIとの対話を「受け身」で終わらせず、
自分の思考を重ねていくことで、はじめて「自分のアイデア」として輪郭を持ちはじめる。
私はそう感じています。
AIとの対話をふくらませる道具として
AIとやり取りをしていると、たくさんのアイデアが短時間で出てきます。
でも、それらを「ふくらませていく」「自分のものにしていく」ためには、
ちょっとした補助線があると助けになることもあります。
そんなときにもアイデアプラント製品を使っていただきたいです。
たとえば、
「アイデアの型」というツール。
これは、「発想を広げるための型」を一覧化したもので、
アイデア発想法として定番の「SCAMPER(スキャンパー)法」を元に作られています。
AIから出てきたアイデアに対して、視点を加えるヒントを与えてくれますし、
自分の意見を書いたり、付せん紙に書いて貼ったりもできます。
こういったツールを使うと、
「AIが出してくれたアイデア」を、自分の手でふくらませるための切り口をたくさん持つことができます。
たとえばこんな、一人ブレスト
AIとやり取りをしながら、思いついたアイデアに自分なりの視点を加えていく。
それは、チームではなく一人でもできる「対話型のブレインストーミング」とも言えるかもしれません。
たとえば、こんな流れです:
1.AIにブレストのテーマに沿った質問をして、ざっとアイデアを出してもらう
「〇〇に関する新しいサービス案を考えてください」といった問いかけからスタート
2. 出てきたアイデアを、眺めてみる
そのままよさそうなものがあればメモしてもいいし、違和感のあるものがあっても気にしなくて大丈夫
3. 「アイデアの型」などを使って、自分の視点でふくらませてみる
「アイデアの型」には、着想を得られやすいように問いの形で言葉が書いてあります。AIが生成してくれたアイデアに適する問いを探すのもよいですね。
4. 気になったアイデアを、さらにAIに問い返してみる
「アイデアの型」に書いてある問いをそのままAIに投げてかけてみてもよいでしょう。さらに思いついたあなた自身からの問いももちろんOKです。
このように、AIとのやり取りを起点にしながらも、
自分の視点でアイデアをふくらませ、再びAIと対話するというループをつくっていくことで、
一人でも創造的なやりとりが続けられます。
大切なのは、「AIから何が出たか」だけではなく、
そのアイデアに対して、あなたがどう反応するかだと思うのです。
おわりに
AIは、たしかに私たちの発想を助けてくれる存在です。
でも、考えることそのものを手放すと、
いつのまにか「自分の視点」も一緒に失ってしまうのではないか。
そんな問いを、この記事ではずっと心のどこかで投げかけていました。
AIにアイデアを出してもらうことは、とても便利です。
でも、出てきたものに対して「あなた自身はどう思うのか?」と問い直す時間は、
これからの創造にとってますます大切になっていくように感じます。
問いを持ち続けること。
立ち止まって、自分の言葉で確かめてみること。
その積み重ねが、「AIと共に考える」というこれからの姿勢なのかもしれません。